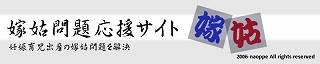
![]() 遠方から孫の顔を見に来るとき
遠方から孫の顔を見に来るとき
![]() ご近所の息子夫婦宅へ孫の顔を見に来るとき
ご近所の息子夫婦宅へ孫の顔を見に来るとき
![]() 昔の育児法と今の育児法。違いを認めてね
昔の育児法と今の育児法。違いを認めてね
![]() 赤ちゃんを抱っこする時の気遣い
赤ちゃんを抱っこする時の気遣い
![]() 赤ちゃんに食べものを与えるときの注意点
赤ちゃんに食べものを与えるときの注意点
![]() 他の赤ちゃんと比べないでね
他の赤ちゃんと比べないでね
![]() 産後の手伝いとは赤ちゃんを抱っこすることじゃない
産後の手伝いとは赤ちゃんを抱っこすることじゃない
![]() 「嫁」と「娘」できるだけ平等にお願いします
「嫁」と「娘」できるだけ平等にお願いします
嫁が産院から退院してきた後、遠方から、息子夫婦の家に孫の顔を見に来られるかたも多いと思います。その場合、息子の家に泊まるのは、できれば避けてあげた方が良いと思います。
初めての育児は、本当に修羅場です。「私が手伝ってあげるわ! 私の出番よ!」と思われるお姑さんもおられるかと思いますが、慣れない育児にストレスがかなりたまって、少し精神状態が不安定になってしまうママも多く、実母とさえ険悪な雰囲気になってしまう嫁もいるのです。
初めての赤ちゃんのお世話で、気持ちはいっぱいいっぱい。夜泣きで夜もほとんど眠れない。それなのに、お姑さんやお舅さんに気を遣い「接待」までしなくてはいけない。そんな新米ママの気持ちを、どうか思いやっていただけないでしょうか。
しかし、遠方から来ていただく場合、日帰りでというわけにはいきませんよね。
できれば、近場のホテルをとっていただけると、嫁としては「なんて気の利いたお義母さん、お義父さんだろう!」と思うのではないでしょうか?
も
ちろん、「あら、そんな他人行儀な」と思う嫁もいるでしょう。ですので、まず嫁に、「そちらへ行くのだけれど、ホテルを予約しようと思うの」と訊いて、そ
の反応をみてみるのが良いのではないでしょうか? 息子に訊くと、嫁に確認もせずに「うちに泊まっていいよ」と即答してしまう場合がありますので、ぜひ、
まず嫁に確認してくださいませ。
ホテルに宿泊する場合でも、一日中息子宅にいるのではなく、できれば一日につき、数時間だけおじゃまするといったほうが無難かと思います。三日間ホテルに滞在するのであれば、一日に一、二時間程度といった感じですね。
また、ホテルから息子宅へ向かう場合は、お昼時を避ける、もしくは人数分のお昼を持参するのが良いかと思います。出来るだけ、嫁に家事をする手間を省かせてあげてください。
もちろん、事前に行く時間を連絡し、その時間に訪問して良いかを訊いてくださいね。
「もう、何をさておいても、あの小さな手、つぶらな瞳、あいくるしい表情を見たい!」
きっとこう思われているお舅さん、お姑さんも多いのでは?
そうなんです。赤ちゃんって本当にかわいいですよね。自分が子育てしていた時の、あのなんともいえない切ない記憶を、まざまざと思い出させてくれる存在。それが赤ちゃんなんですよね。
でもね。
だからといって、頻繁に赤ちゃんに会いに来るというのは、どうかご遠慮願いたいのです。新生児を子育て中のママは、本当に疲労困憊状態のことが多いのです。
新 生児を育てているママの睡眠時間は、大げさでなく二、三時間だということも珍しくありません。精神的も身体的にも丈夫で頑丈な女性が、「産後鬱」状態にま
でなることもあります。特に初めてのお子さんを育てているママは、せっぱ詰まった精神状態のかたが多いのではないかと思います。
たった三十分でもいい。寝たい。寝たい。寝たい!
そんなことを切実に思っているママのところへ、しょっちゅう呑気(言い方が悪くてすみません)に、るんるん気分でやって来るお姑さんのことを、なかなか好意を持って受け入れることは難しいと思うのです。
息子が在宅の土日をねらって、来訪するお舅さんお姑さんもおられるかと思います。これも、実は気を付けていただきたいのです。
ママは、平日、孤軍奮闘で育児をしています。ママにとっての土日とは、
「ようやく、夫とゆっくり会える」
「夫に話をいっぱい聞いてもらいたい。赤ちゃんを見ていろいろ二人で話をしたい」
「夫に赤ちゃんの面倒をみてもらって、美容院や買い物に行きたい」
こんな感じで、土日の夫との時間を、本当に心待ちにしているママも多いのです。できれば、なるべくそっとしておいてあげてほしいのです。
でもやはり、「それでも、赤ちゃんを見たい! 赤ちゃんの成長を見守りたい!」そう思われるお姑さん、お舅さんのお気持ちもとてもよくわかります。
実際、赤ちゃんの成長は本当に早いです。二週間会わなかっただけでも、顔つきが変わっているなんてこともあるでしょうしね。
また、嫁が里帰り出産をした場合は、嫁側の親は毎日毎日赤ちゃんの成長を見ることができます。もちろんその反面、色々なお世話の手伝いなど、金銭的肉体的精神的な苦労も発生するのですが。
そんな場合は特に「同じ孫なのに…」と思われるかもしれません。
なので、もしも「頻繁に赤ちゃんに会いたい」とお姑さんが思われているのであれば、できるだけ嫁姑、お互いにメリットがある方法を模索してみてはいかがでしょうか。
例えばですが…。
嫁は育児中、自分の時間がほとんど持てません。
なので、お姑さんがいらっしゃる間、嫁が自由に買い物やヘアサロンなどに行く時間を提供する。
睡眠時間が圧倒的に足りないママもいます。
孫を見ている間、お嫁さんには寝ていてもらうのはどうでしょうか?
でもこのやり方がスムーズに行くには、ちょっと工夫が必要。独りよがりの「親切の押しつけ」ではだめ。やはり相手の希望を聞いて欲しいのです。お姑さんと嫁の「したいこと・してほしいこと」が一致したときにのみ、有効だと思うのです。
例えば、「そうだ、私、あなたに変わってご飯を作ってあげるわ!」「掃除をしてあげるわ!」と申し出ていただいても、勝手に炊事スペースを使われるのがとてもいやな嫁もいますし、掃除のやり方にこだわりがあり自分以外はやってほしくないという嫁もいます。
全ての「してあげよう!」が相手にとってありがたいかというと、そうではありませんよね。
ま
た、嫁側から「お姑さんが来ている間、私はヘアサロンへ行きたいでーす、体を横にしたいでーす」なんて言い出せるかたは少ないと思います。ぜひ、お姑さん
側からざっくばらんに、「私、赤ちゃんが見たいのだけれど、その間、あなたが体を休めたり、どこかへお出かけするなんてどうかしら?」と希望を訊いてあげ
てください。
そして、
「して欲しいことはなにかしら?」
「してはいけないことってどういうことかしら?」
と必ず訊いてください。
できれば、その内容を紙にメモすると、嫁は、「あ、きちんと私の言うことを理解してくださっているわ、これなら任せられるわ、安心だわ!」と、お姑さんへの信頼度もアップすると思うのです。
もちろん、嫁が「してほしくない」と言ったことは、絶対しないでくださいませ。たとえ、隠れてこっそりとでも!
「我が子の命をお姑さんに預けた」という嫁の気持ちを、踏みにじることになります。
ぜひ一度、今売られている育児雑誌を一冊買って、読んでみてください。
たった十年ほど前の育児方法ですら、現在の育児方法に比べれば、「古い手法」になりつつあるのではないでしょうか?
・「抱き癖がつくから抱っこはしなくても良い」
・「粉ミルクはだめだ。母乳で育てなさい」
・「母乳が出るには、●●を食べるのが絶対に良い」
・泣いている赤ちゃんを必死にあやす嫁に対し、「貸してみなさい」と赤ちゃんを取り上げて自分があやす
・「湿疹がいっぱいでかわいそうね」
などという言葉・行為は、本当につらいことが多いのです。
今では、好きなだけ赤ちゃんを抱っこしても良いとされています。粉ミルクもちゃんと栄養があります。反対に、母乳育児もとても素晴らしいものとして認識されているのです。
なかでもよく聞く言葉で、嫁が一番つらいのは、
・「おっぱい、足りてないのでは?」
の一言。
頻繁に嫁におっしゃってはおられませんか?
これも本当に傷つく一言です。悪気はないかどうかではなく、出た言葉が問題だと思うのです。
母乳育児は
・授乳間隔のコントロール
・母乳に良い食事
などなど、母親が頑張らなくてはいけない部分もあります。
どんなに頑張っていても、育児疲れ等により乳腺炎になってしまうこともあります。
![]() 乳腺炎について説明してあります。
乳腺炎について説明してあります。
母乳育児を嫁が頑張っているのであれば、ぜひ、そっと応援してあげて欲しいと思います。
初めての育児の場合は特に、嫁の気持ちは不安でいっぱい。現在ではとてもたくさんの良い育児書が出回っていますし、ママはそれを熟読しているはず。いろんな育児知識は持っているはずです。
どうか、新米ママの「これから頑張って育児するぞ」という気持ちに寄り添っていただけるとうれしいです。
一つ失敗し、そして学んでいく。そうやって新米ママは少しずつ頼もしい母親になっていくのだと思うのです。
また、同様に、
・「赤ちゃん、どうか大切に育ててね」
・「どうか、風邪をひかせないようにね」
・「どうか、怪我させないようにしてね」
これも過度に言い過ぎると、プレッシャーに感じるママが少なくありません。
もちろん、「孫が余りにもかわいい! 自分が守れない分、どうしても嫁に守って欲しい」という、悪気のない気持ちから出てくる一言だろうということは、充分、わかります。
でもね。
赤ちゃんに怪我をさせたいママがいるでしょうか?
赤ちゃんを風邪をひかせたいママはいるでしょうか?
小さな赤ちゃんが風邪をひけばオロオロして「自分が変わりたい」と思うママ、一歩先の安全に気を配っているママが大半だと思います。
そう。お姑さんお舅さんと同じ気持ちだと思うのです。言われなくてもね。
赤ちゃんを大切に大切に育てていても、いずれ風邪をひきます。怪我無く成長するのが一番ですが、いずれ、どうしてもママの一瞬の隙を突いて怪我が起こることもあるのです。
余りにも危なっかしい(たとえば、寒い冬の深夜に、性急な必然性もないのにショッピングに連れ出すことや、車の往来の多い道路で子どもを遊ばせて親の目もない…などがあたるのでしょうか)場合ならともかく…ですが、どうか新米ママを信じてあげてくださいませ。
「赤ちゃんが可愛くて可愛くてたまらない!」という、お姑さんのお気持ちはとてもよくわかるし、ありがたいです。
でも、病院にお見舞いに来ていただいたり、家に孫を見に来ていただいたりした時に、挨拶も早々、嫁の目も見ずに、いきなり嫁の腕の中から「ガバッ」と奪い去るように赤ちゃんを持っていくのは、あまり感じの良いものとはいえないなぁと思うのです。
野
生の動物の母親には、産まれたての我が子に近づくもの全てをものすごい勢いで威嚇し、殺してしまうものがいます。普段は温厚でおとなしいのに、です。そう
しないと、無防備な産まれたての我が子を守ってやることが出来ないので、そのように本能にプログラムされているのだと思います。
嫁の中にも、少なからず、自分や夫以外の誰かが我が子を抱っこするということに、どうしても嫌悪感を抱いてしまうママがいるのです。
もちろん、その母性からくる”嫌悪感”という本能を、理性でコントロールするのが、社会性を持っている人間のつとめだと思います。
文字通り命がけで赤ちゃんを産んだ直後の母親は、「自分の子!」という意識がとても強いと思います。
できれば「抱っこしても良いかしら?」と嫁に一言聞いていただけると、本当にうれしいです。
実は、嫁姑問題において、「赤ちゃんと食べ物」のトラブルは、一、二を争うほど多いと思っています。
赤ちゃんの体内に入っていく食べ物。アレルギーなどがある場合、時には「死」にも直結する食べ物。なので余計に、そこに嫁姑の意見のすれ違いトラブルが発生すると、他のトラブルに比べて、おおごとになってしまうと思うのです。
まずは、今の育児書の離乳食などのページを一読されるのが、一番の理解の早道だと思います。
「これくらいあげてもいいじゃない。おおらかにいきましょうよ。神経質だとだめよ」そうおっしゃるお姑さんのお気持ちもわかります。でも、それは、今の育児においては「おおらか」では済まされないようなこともあるわけです。
赤ちゃんへ食べ物をあげるという行為は、ダイレクトに「赤ちゃんの生命に関わること」です。だからこそ、嫁は、慎重にいこうと思っていると理解していただけるでしょうか。
「おおらかに!」も大切なのはわかります。でも、それ以上に、「慎重に」育てていくことも大事にしている嫁の気持ちをわかっていただけるとうれしいのです。
「これを飲ませたけれど、息子は虫歯にはならなかった」「これを食べさせたけれど、息子はなんともなかった」「これは、昔は当たり前だった」たしかにそうかもしれません。
でもだからといって、息子と孫の体質の違いも無視し、嫁の育児方法を一足飛びにして、「だから、孫にあげてOK!」となるわけではないですよね?
そうそう。
「赤ちゃんが欲しがっていてね。よだれをだしてお口をぱくぱくさせて、手を伸ばしていたの。だから、だめかなーと思ったけれど、●●を食べさせちゃった」とおっしゃるお姑さんもおられるかもしれません。
い
えいえ、違うのです。ある月齢の赤ちゃんは、なんでも口に入れたくなります。おもちゃであろうが、消しゴムであろうが、携帯電話であろうが、何でもかんで
もお口をぱくぱくさせながら手を伸ばし口に入れようとする時期があるのです。おなかがすいているからではなく、それが食べたいからではなく、「そういう時
期」なのです。
どうか、食べたそうにしてかわいそうだという理由で、大人用の食べ物を食べさせるのは遠慮してくださいませ。きっと、お姑さんが想像されている以上に、「それはいやだ」と思っている嫁は多いのです。
そしてどうか、大人ご飯を食べさせないようにしているママを横目に「かわいそうねぇ。食べたそうにしているのに」などと、ボソッとつぶやくのはやめてくださいませ。ママとしては子どものため、がんばっているのです。認めていただけるとうれしいです。
また、ほかにも気をつける点があるとすれば、
![]() 大人が食べて柔らかくしたものを吐き出して、それを与えることはやめてください。
大人が食べて柔らかくしたものを吐き出して、それを与えることはやめてください。
![]() 大人が使ったスプーンで、赤ちゃんに食べ物をあげるのはやめてください。現在では、虫歯菌が移る原因として、検診にてかなり厳しく指導されています。
大人が使ったスプーンで、赤ちゃんに食べ物をあげるのはやめてください。現在では、虫歯菌が移る原因として、検診にてかなり厳しく指導されています。
![]() 大人が食べるものを「これくらい、昔は食べていた」と、与えることもやめてください。スルメなど与えてみたくなるのはわかりますが、NG。ビールの一滴ぐらいなどと言って、箸の先にお酒をつけて赤ちゃんになめさせて反応を見るなんてもってのほか!!
大人が食べるものを「これくらい、昔は食べていた」と、与えることもやめてください。スルメなど与えてみたくなるのはわかりますが、NG。ビールの一滴ぐらいなどと言って、箸の先にお酒をつけて赤ちゃんになめさせて反応を見るなんてもってのほか!!
以上のことも、どうか気をつけてくださいませ。
ま た、赤ちゃんお菓子をあげたいと思われるのならば、なるべく低月齢用のお菓子(例えば孫の月齢が七ヶ月なら、五ヶ月から食べられるようなお菓子)を選んで
あげると良いかと思います。そして、お菓子を与える場合、「これをあげたいのだけれど」と一声かけてくださいませ。この一言があるかないかは、本当に印象
が違います。
自分の娘の赤ちゃんや、ご近所の赤ちゃん。
嫁の赤ちゃんと同じくらいの月齢の子がいた場合、ついつい比べてしまうのですよね。
「●●さんとこの赤ちゃんはもう歩いたよ」
「●●さんの赤ちゃんはこんなものを食べているらしいよ」
「●●さんの赤ちゃんはよく寝て手が掛からないらしいよ」
やはり上記のような言葉は避けていただけるとありがたいです。
悪気がなく、ただ事実を述べているとしても、それが時として新米ママを傷つけることがあります。
特に、お姑さんに娘さんがおられる場合、そのお子さんと比べられるのは、かなりつらいです。どうしても嫁は、「あぁ、お義母さんは、自分の娘の子のほうが何倍もかわいいよね」と思ってしまいがちです。
「赤ちゃん、なかなか大きくならないわ」
「おっぱいは足りているのかしら」
「離乳食は順調なのかしら?」
「ほっぺたの湿疹は大丈夫なのかしら?」
ご心配されるお気持ちはわかります。でも、一番、気を付けて見ているのはママ。おかしな事、気になる事があれば、きっとお医者様が何か言っているはずです。
ママは二十四時間ベビーの表情、しぐさを感じ取りながら生活しています。ママの目を信じてあげましょう。
それでも気になるようでしたら、まず、嫁の夫である息子にそっと尋ねてみるのが良いのではないでしょうか?
嫁の産後のお手伝いに行く。その光景を想像して、ご自分が何をしている場面を思い浮かべますでしょうか?
赤ちゃんを抱っこしている場面でしょうか?
「産後の手伝い」とは、泣いている赤ちゃんを抱っこしてあやしたりすることだと考えているかたがおられるかもしれません。でも違うのです。基本的には、
「産後の手伝い」とは、「育児をすること」ではありません。
「産後の手伝い」とは、「嫁が出来ない家事を手伝うこと」です。
中には、産後の手伝いと称して息子(娘)宅へ行き、「赤ちゃんを抱っこしておいてあげるから、あなたは掃除、洗濯なんでもしてね」とおっしゃるかたがおられるのです。
違いますよね?
育児、赤ちゃんのお世話は、孫を産んだ嫁がするものです。
赤ちゃんが泣いていたとしても、率先して抱っこしてあやしたりするのはやめてくださいね。
「私のほうが育児のベテランよ。私だったら泣きやませてあげられるもんね」そう思って、嫁から泣いている赤ちゃんをガバッと奪い取り、なかなか返してくれないかたもおられるのではないでしょうか。
また、嫁の育児の仕方が気に入らないといって、「あれはダメ」「それはダメ」と否定するのも、どうぞやめてくださませ。その育児方法を実践なさるのは、ご自分の息子・娘を育てられたときで充分ではないでしょうか。育児の方法は、百人いれば百通り。そうでしょう?
明らかに、孫の命に関わるような事であったり、虐待と思われるような事以外は、どうか「嫁の育児」を尊重してくださいませ。
心配で不安でしょうが、ぜひ、育児は嫁にまかせてください。
そして、そっと、食料の買い出し、洗濯、掃除などを手伝っていただけるとうれしいです。
自分がおなかを痛めて産み、骨身を削って十何年も大切に育ててきた「実娘」
それと同じように育ててきた息子と結婚し、ほんの数年しかつきあいのない「嫁」
同じように平等に接しろというのは難しい話です。
それは重々わかっているのです。
でも、その差をあからさまに感じさせるような言動は、とても嫌な気分になるものです。
具体的にあげてみると…
・皆で集まったときに、娘だけに何か特別に渡したりしていませんか? 出来るなら、嫁が見ていないところでそっと渡すのがいいのではないでしょうか。
しかし、こそこそしすぎるのもかえって嫁の心の中に疑心暗鬼を生み出す可能性もあります。その辺りは難しいですよね。
・嫁の前で、娘夫婦や、その子ども達の話題「ばかり」を延々と話したりしていませんか?
嫁がニコニコと聞いているから大丈夫…というわけではないかもしれません。姑さんのお話を「つまらない」顔をして聞くことができる嫁ははなかなかいないと思うのです。無理してでも「そうなんですかー! ふふふ」と笑って聞いたりするものです。
ましてや、娘や娘の子の「自慢話」は、謹んでおいた方が吉かもしれません。聞いてくれるのは嫁だけだものとおっしゃるお姑さん。なぜ他の人達が聞いてくれないのかをぜひ考えてくださいませ。
・嫁には「私たちの実家で正月や盆を過ごしなさい」「嫁は夫の実家の側に住むのが当然」「夫親の介護は、嫁の勤めよ」などと勧めるのに、実娘には「実家(姑さんの家)で正月ゆっくりしなさいよ」「私たちの側で住みなさいよ」「娘の嫁ぎ先の親の介護なんてさせたくないわ、あの子は体が弱いから」などと、言っていませんか?
それは余りにも「都合のいい話」ですよね? 嫁は何も言わないかもしれませんが、心の中で「どういうつもり?」と不満を抱えている可能性が大きいのではないでしょうか。
どうでしょう。
ほんの些細なこと、ありきたりな言動なのかもしれません。
でもほんの少しだけ気を利かせて頂けると、嫁はとても嬉しく感じると思うのです。
![]() 「嫁姑問題応援サイト」が、雑誌「たまごクラブ」で紹介されたときの記事
「嫁姑問題応援サイト」が、雑誌「たまごクラブ」で紹介されたときの記事
よく読まれている記事
![]() 嫁とコミュニケーションを取るとき
嫁とコミュニケーションを取るとき
![]() うわべだけの育児の手伝い?
うわべだけの育児の手伝い?
![]() 妻が風邪をひいたとき
妻が風邪をひいたとき
コンテンツ
![]() 妊娠時の嫁姑問題を解決
妊娠時の嫁姑問題を解決
![]() 出産時の嫁姑問題を解決
出産時の嫁姑問題を解決
![]() 育児中の嫁姑問題を解決
育児中の嫁姑問題を解決
![]() 贈り物にまつわる嫁姑問題を解決
贈り物にまつわる嫁姑問題を解決
![]() 嫁とのコミュニケーション
嫁とのコミュニケーション
![]() 帰省時の嫁姑問題を解決
帰省時の嫁姑問題を解決
![]() 帰省時の嫁姑問題を解決(細かい注意点)
帰省時の嫁姑問題を解決(細かい注意点)
![]() 息子宅での嫁姑問題を解決
息子宅での嫁姑問題を解決
![]() 嫁姑問題と夫
嫁姑問題と夫
![]() 嫁が言えない夫への一言達
嫁が言えない夫への一言達
![]() 男の子育児の本音
男の子育児の本音
![]() このサイトを夫に見せる時の注意点
このサイトを夫に見せる時の注意点
![]() 管理人からのお願い
管理人からのお願い